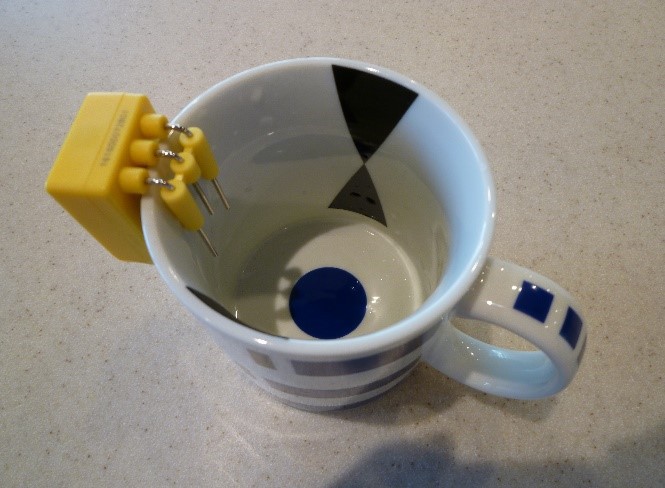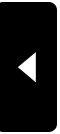地域での孤立、孤独を防ぐ「修徳ふれあい食堂」が2016年10月からスタートしました。
地下鉄五条駅近隣の特別養護老人ホーム&児童館で、地域のこどもたちの居場所づくりとして夕食の提供が始まりました。
実際には地域には夕食づくりで困っている人たちがたくさんいることがわかり、
当初の「こども食堂」から、「ふれあい食堂」に変更となりました。
子どもたちばかりでなく、地域の一人暮らし高齢者や乳幼児を抱える若いお母さんなども夕食に来られるからです。
年齢差もありますが、夕食に参加した皆さんは地域のボランティアや学生ボランティアと
食後の会話も楽しみ、笑顔になって帰られています。
学生たちは、赤いバンダナを頭に巻いて、ハンドマッサージ、乳幼児のお世話、小学生の宿題の支援、高齢者の方々との会話、食事の配膳手伝いなど、自分たちが得意なことをできる範囲で行っており、
学生自身も楽しみながら地域での「共生」の必要を実体験してくれています。
「参加の皆さんと一緒に食べるカレーの味は最高だ」と言ってくれています。
「ふれあい食堂」は原則、第三金曜日18時からのスタートです。
学生ボランティア募集中です。