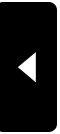社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験まであと40日を切りました。
本来であればのんびりしていただきたい年末年始ですが、
来年2月2日(土)・3日(日)の精神保健福祉士・社会福祉士国家試験に向けて12月から受験勉強の追い込みが始まります。
お正月をのんびり過ごしてしまうと受験勉強が間に合わなくなるので、受験生である4年生は毎日6時間とか7時間とか受験勉強を行っています。
そんな勉強をサポートする精神保健福祉士受験対策講座。
授業が終わった年末2日間、そして授業が始まる年始2日間に過去問・模擬問を解き、教員が解説するスタイルで受験対策を行っています。
4年生の先輩の受験ノートをちょっと見せていただきました。
まだ受験勉強を始めたばかりというのが分かる内容ですね。
ここから勉強を積み重ね、年明け月半ば頃には教員が答えられないような難しい質問をしてくるようになります。
そんな4年生をフレーフレーと応援しながら2月の国家試験を迎えます。








 滞在先のモテキ・ハウス(寮)にて
滞在先のモテキ・ハウス(寮)にて 作ったカレーでお・も・て・な・し
作ったカレーでお・も・て・な・し 講義風景
講義風景 地域包括型高齢者デイサービスにて交流
地域包括型高齢者デイサービスにて交流 知的障がい者通所施設で交流
知的障がい者通所施設で交流 知的障がい者通所施設で日本の歌披露
知的障がい者通所施設で日本の歌披露 特別支援学校(STU)訪問
特別支援学校(STU)訪問 保育園で日本の歌披露
保育園で日本の歌披露