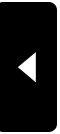「"住環境"研究室」のゼミ研究を紹介します。
研究タイトルは「屋外環境と快適性に関する実験研究」
都心において建築物の密集の回避を目的に、公共空間を増やすためのオープンスペースの確保が促進されています。オープンスペースは単なる場の提供だけではなく、そこで人の交流が活発に行われることで街が活気づくことが期待されています。そのためには場が質的に良い環境であることが必要です。
本研究は大学キャンパスの屋外休憩場所(芝生中庭、茶室庭園、ユニソン会館北側)を取り上げ、
自然気候に曝露された屋外で被験者評価実験を行いました。
そして、環境要素と人の感覚との関連を把握し、快適な屋外環境のありかたを検討しました。
またVR実験を行って、緑樹の視覚情報が温冷感に影響を与えるかどうかについて検討を行いました。
研究方法は、
1)大学のキャンパスの植栽状況など環境の異なる3地点
2)気温・湿度・気流・照度・日射量・騒音レベルを機器を用いて実測。また被験者に感覚・心理評価は温熱感、湿気感、風量感、明るさ感、騒静感を5段階、場の快適感、場の印象、総合評価として[小休憩に適している]を4段階で評価させた。実験期間は5月から10で毎月実施しました。被験者は学生のべ19名である。
3)VR実験は、屋外環境調査実験の地点を360°カメラにて撮影した対象画像を、VRゴーグルを装着した被験者に、温熱環境を25°湿度40%に調節した実験室で評価させました。
結果、
それぞれの地点の現状を把握し、環境に手を加えることでより快適性を向上するための工夫として、
芝生中庭は気温や日射量が多いことから、暑さや眩しさを感じる頭上や周囲に日射を遮る樹木を増やす、
茶室庭園は、暗く湿度が高いことから、緑量を減らす、あるいは休憩地点と植栽に距離をとるなどして通風の改善をする、
ユニソン会館北側は、コンクリートに囲われて植栽がないことが総合評価を低くしていることから、例えばプランターを設置するなど植栽を増やす工夫をする。
などの提案を導き出しました。
またVR実験より、視覚情報だけでは温冷感は変わらないことが明らかとなりました。
 屋外実験風景
屋外実験風景 VR実験風景
VR実験風景