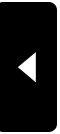住環境ゼミは、6月19日、
上賀茂神社の社家町と、社家の錦部家旧宅(現、西村家別邸)を見学しました。
社家とは神官の住居で、上賀茂神社のように多くの社家が集まっているのは全国でも珍しいそうです。
上賀茂神社は 大学からバスで約10分と近いです。
上賀茂神社境内を流れる "ならの小川" は 明神川と名を変え、水路のように社家町を流れます。
社家町の景観は、明神川に添って趣ある土屏が連なる様子が特徴です。
(上賀茂神社に参拝)
(明神川)
一軒一軒の社家へは川に架かる石橋を渡って門をくぐります。
錦部家旧邸の見どころは庭です。
1181年(養和元年:安徳天皇の時代)に当時の上賀茂神社の神主が作庭したものです。
京都にお寺の庭は多くあるけれど、神官の庭は珍しいとのこと。
庭の緑豊かな樹木や苔生した岩の配置は立体的で、無限の広がりを感じます。
庭の主な構成は、曲水の川、禊の井戸、降臨石です。
曲水の川は、明神川の水を庭に引きこんだ鑓水で、平清盛が活躍した当時、"曲水の宴"のために設けられた小川とのこと。
禊の井戸は、神官が神事の前に身を清めた井戸です。
降臨石は、上賀茂神社のご神体を形取った石組
厳粛に日々繰り返される禊の儀式、客人を招いての宴、草木を愛で移ろう季節を歌に詠む、、、
この庭とともに展開されたであろう昔の神官の暮らしがしのばれます。
(お庭)
また、庭を巡る水はきれいな水でもとの明神川に還す工夫がされています。奥池の池底の一部を丸く窪ませることで、泥やごみを沈殿させ川に流れ込まないようにする、いわゆる現在の「排水桝」を設けていることや、生活汚水は水口(下水処理専用井戸)でろ過するなど、排水リサイクルシステムが設けられています。
平安人の水を大切にする強い思いを知ることができます。
(科学技術進展した現代社会において、水汚染が無視できない重大な環境問題になっているのはなぜか。)
家屋は江戸時代のもので数寄屋造り、掛け込み天井です。
6月、初夏の候、
沙羅の白い花弁と甘い香り、清々しい青紅葉、涼やかな曲水、無双窓の微風
五感にやさしい心地よさです。
今回、社家、社家町を訪ね、風情ある庭が、見た目の美しさに環境配慮も備えていたことなど 昔の生活文化の奥深さを学ぶ、貴重な体験となりました。
モダン住宅に住んでいる学生らも、この古の空間にすっかり癒されたようです。
<家屋内にて>