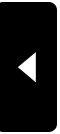「基礎演習Ⅱ」という科目は、
衣、食、住、家族、福祉をテーマに体験学習を通して、幅広い学問領域にふれることが目的です。
今回は、福祉学分野 「ささえる」を紹介します。テーマは "車いす体験" です。
車いす体験をしました!
車いす体験を通して、援助の仕方やコミュニケーションの方法について学びます。
体験は、
①無言のまま車いすで学内を回る。
②途中から、お互いに話をしながら学内を回る。
役割を交代して①、②を体験する、 です。
体験ののち、ディスカッションをします。
ディスカッションは
①のときの気持ちについて、話し合う。
どのような気持ちだったか。どのようにしてほしいと思ったか など
②になって、気持ちに変化があったかどうか、話し合う。
どのような気持ちに変わったか。なぜそのような気持ちに変わったか など
①②から、援助するときにどのようなことが大切か考える。
車いす利用者への援助として、どのようなことに配慮し、どのようなことが大切かを一人ひとり考える。
体験とディスカッションを通し、車いす利用者の思いを感じ取り、どのような手助けや関わり方をしたらよいのかを考えます。
学生たちは、
無言のまま車いすで学内を回った時は
「怖くて不安だった。急な動きに驚いた。振動が伝わった」などの感想を、
一方、会話しながら車いすで学内を回った時は
「安心した。安全だった。楽しかった」ようです。
車いすを押す人は座っている人の不安や緊張が和らぐように、行先や障害物等の情報を正確に伝えることが大切です。
また、速度や周囲の状況(車や歩行者等)にも気を配ることが大切です。
車いす体験を通して、相手の立場に立ったコミュニケーションの必要性を学びました。