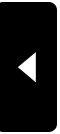受験しようかどうか迷っている人、必見! 前報(その1)は新入生アンケートから「何が入学の決め手」になったのかを報告しました。
今回は質問その2。
本学科の「入学後に気づいた魅力」です。入学して半年たったところで 「入学後に気づいた魅力」を挙げてもらいました。半年学んで、どんな魅力に気づいたのでしょう。
それでは、まず第3位。同率で2つ解答がありました。
「先生が優しい」、「少人数で学びやすい」の2つがランクインしました。
第3位 「先生が優しい」
「先生が親切」、「先生が優しい」。ちょっと大学の入学後の魅力として挙げられたものとしては意外かもしれません。福祉生活デザイン学科の先生は学生さんの結果で判断せずに「プロセス」を大切にしています。自分なりに一生懸命、全力を挙げて臨んでいる学生さんに対してはたとえ結果が十分でなくても「良く頑張ったね」と声をかけています。大学はまだまだ成長の場です。成長を大切にする姿勢が先生たちにみられる結果かもしれません。
そしてもうひとつの第3位、「少人数で学びやすい」、これは入学の決め手にも挙げられていましたね。「少人数なので先生に質問しやすい」、「ゼミとか少人数だから深く教えてもらえる」などが挙げられています。1年生から始まる基礎演習では2年間10人前後のクラスで担任の先生とともに福祉生活デザイン学科の基礎を学びます。たとえば基礎演習Ⅰでは大学での授業の受け方のコツやレポートの書き方について集中して学んでいきますし、基礎演習Ⅱではすべての領域の「実習」を体験していきますが、このクラスがホームルームのような役割を果たしています。あれこれ何でも相談できるサイズのクラスです。
続いて第2位。第2位 はなんと「校舎がきれい・整っている」です。
「校舎がキレイ」「教室がきれい」といった施設がきれいという回答や「さまざまな設備があるので過ごしやすい」「設備が整っている」という施設が整っている回答が第2位です。なかでも学生のイチ押しは「トイレがきれい」。いつも清掃の職員さんがあちこちで黒板やホワイトボード、そして廊下からトイレまでをきれいにしてくださっています。ホームページからは分からない、本学の魅力ですね。
そして栄えある第1位は…第1位 「幅広く学べる」 です。これも「入学の決め手」にも挙げられていましたね。実際に入学して半年、いろいろな学びを体験して「学科の中身の種類の多さ」、「広い範囲の学習」として挙げられていますが、「1年間各分野を学ぶことができるところ」と挙げられている回答もありました。1年生でひととおり学び、2年生から自分の専門を決めて深く学ぶ。本学科の最大の魅力です。入学後、改めてしっかりと気づいていただけるようです。
さて、ホームページや見学ではなかなか気づけない「本学科の魅力」を知っていただけましたでしょうか。みなさまのご入学をお待ちしておりますね。
(2019年4月 フレッシュマンセミナーでの集合写真)