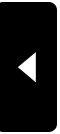精神保健福祉士の受験資格を取得することができます。
2019年7月25日(木)、本学マリア館ガイスラーホールで、「精神保健福祉実習報告会」を開催しました。
(報告会の様子)
4年次生 7名が本年2月〜3月に、精神科医療機関と作業所の2ヵ所で合計150時間(約23日)実習させていただき、以後、大学の授業で実習の振り返りをしながらその成果をまとめ、この度発表させていただきました。
本学の実習報告会は、実習に行った4年次生と実際に実習指導を担当してくださった精神科医療機関や作業所の実習指導者が合同で行うことを特徴としています。
今回もとても忙しい中時間を割いて6名の実習指導者が本学にお越しいただき、
学生の発表に対し、コメントをいただきました。
学生にとってはとても緊張する発表となりますが、実習指導者のみなさまから、改めてその学生の長所や強み、そして実習時の様子、
さらに発表からみえてくる学生の学びの深まりについてのコメントは、学生にとってうれしい機会ともなっています。
実習指導者のみなさま、本当にありがとうございました。
4年次生は、就職活動がひと段落ついた学生が多いので、
これから卒業論文の作成と国家試験対策に臨んでいきます。
全員が社会福祉士、精神保健福祉士のダブル合格を目指しています。
夏休みにも大学において受験対策を重ねます。
自分の力を最大限発揮できるよう、教員も精いっぱいサポートしていきます。
(発表会場:本学、ガイスラーホール)