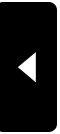産官学連携活動に積極的に取り組んでいます。
平成31年1月に京都市中央卸売市場と協定を結びました。
この活動の一環として、京都市中央卸売市場の
第一市場長の古井様と、第二市場の林様にお話しいただき、
市場の機能と役割を学びました。
中央卸売市場は、第一市場(水産物部、青果部、漬物、乾物、佃煮、鳥肉、鳥卵などを扱う)と、第二市場(牛、豚肉を扱う)に別れていること。
卸売市場の流通の仕組みについて、
卸売市場で取引するシステムの意味について、生産者側と消費者側の両方の立場からわかりやすく説明いただきました。
近年のネット通販の拡大や流通の多様化のため、取引量は減少傾向ということですが、
安全・安心な食の提供、生産活動の維持、物流の効率化(環境対策)などに、市場は大きな役割を果たしていることを知ることができました。
また、単に、食品の流通だけでなく、京都ブランドを世界に発信したり、
京都の食文化・食育の拠点として市民に向けてのセミナーなど
様々な活動をされているそうです。
古井様、林様、ありがとうございました。
また、京都中央卸売市場のみなさま、
これからの連携活動もどうぞよろしくお願いします。